それでは第146回の解答&解説です。
解説はおなじみ地の守護聖ルヴァ様です。
それではルヴァ様、よろしくお願いします。
A1
はいは〜い。では1問目から考えてみましょう。
1)1列に並んだ少年たちに1人ずつ順番に金貨をあげていきます。あげないことも可能です。
2)彼らの反応は「喜ぶ」か「怒る」のどちらかです。
3)1人目は、1枚以上の金貨をもらうと喜び、もらえないと怒ります。
4)2人目は、1人目よりも1枚でも多く金貨をもらうと喜び、そうでないと怒ります。
5)3人目以降は、直前の2人、たとえば7人目なら5人目と6人目ですね、その2人がもらった合計より1枚でも多く金貨をもらうと喜び、そうでないと怒ります。
6)最終的に、9人のうち半数以上が喜んだ場合はいいのですが、半数以上が怒ったときには9人全員が暴れだしてたいへんなことになります。
という条件で、少年たちが暴れ出さないようにする、金貨の最小枚数は何枚か、という問題でした。
9人のうち5人喜べばいい、ということですね。
では、この条件にしたがって金貨をあげるパターンを考えてみましょう。
ヒント5)の「直前の2人の合計」より多くあげると喜ぶ、という条件を間違えないでくださいね。
さて…
| あげる枚数 |
1 |
2 |
4 |
7 |
12 |
| 合計枚数 |
1 |
3 |
7 |
14 |
26 |
| 反応 |
喜 |
喜 |
喜 |
喜 |
喜 |
こんなふうにどんどんあげていくと、枚数がとっても多くなってしまいます。
9人のうち4人までは怒らせても大丈夫ですから、「あげない」ということをうまく使いましょう。
| あげる枚数 |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
4 |
0 |
5 |
| 合計枚数 |
1 |
1 |
3 |
3 |
6 |
6 |
10 |
10 |
11 |
| 反応 |
喜 |
怒 |
喜 |
怒 |
喜 |
怒 |
喜 |
怒 |
喜 |
このように、1人置きにあげないようにすると、それなりに節約はできますが、まだまだ少なくできそうです。
「あげない」を2人連続して、直前の2人の合計を0枚にしてみましょう。
| あげる枚数 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| 合計枚数 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
| 反応 |
喜 |
怒 |
怒 |
喜 |
怒 |
怒 |
喜 |
怒 |
怒 |
こうすると、あげる枚数はとっても少なくなりますが、6人も怒っていますから、これではダメです。
1人目を「あげない」から始めても同じ結果ですね。
では、もう少し金貨をあげるようにしてみましょう。
| あげる枚数 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
| 合計枚数 |
1 |
3 |
3 |
3 |
4 |
6 |
6 |
6 |
7 |
| 反応 |
喜 |
喜 |
怒 |
怒 |
喜 |
喜 |
怒 |
怒 |
喜 |
怒っているのは4人ですから、これならOKです。
ちょっと順番を変えて、1、0、0、1、2、0、0、1、2 としても同じ結果になります。
1人目を「あげない」から始めると、怒るのが5人になりますから、それではダメですね。
他にもいろいろ試してみてください。
これ以上少ない方法は見付からないと思いますよ。
ということで、これが答となります。
1枚、2枚、0枚、0枚、1枚、2枚、0枚、0枚、1枚
あるいは、
1枚、0枚、0枚、1枚、2枚、0枚、0枚、1枚、2枚 の7枚
いかがでしたか?
いろいろ試行錯誤をして、少なくなるパターンに気が付くこと、でしょうかね。
A2
では第2問を考えてみましょう。
3人の研究員A、B、Cの3人は、『着眼点』『論理性』『文章力』の3要素について7点ずつ持っていて、その7点の持ち点を3つのレポートに余さず振り分ける、ということで、
ヒントから、3人がそれぞれどう得点したかを考える、という問題でした。
ヒントはこうです。
| 1 |
3人の研究員はそれぞれの要素に7点を振り分けましたが、0点をつけることはありませんでした。 |
| 2 |
3人のうち、総得点が1番高かった人と2番目に高かった人の得点差は1点でした。 |
| 3 |
ランディの『論理性』には、3人の研究員は3人とも同じ点数をつけました。 |
| 4 |
マルセルの『着眼点』に対しては研究員3人のつけた点数はバラバラでした。マルセルについては、『論理性』もバラバラの点数でしたし、『文章力』もバラバラの点数でした。 |
| 5 |
どの研究員も、3人につけた点数の小計は同じ点数にはなっていません。 |
| 6 |
ランディの小計は、研究員3人とも6点以上で、総得点は奇数でした。 |
| 7 |
3人の研究員はこんなことを言っています。
| 研究員A |
「マルセル様の『着眼点』と『論理性』にはそれぞれ4点をつけました。私は3点を2回つけました」 |
| 研究員B |
「ゼフェル様には、3つの要素すべてに3点以上をつけました。『論理性』の要素には3人にすべて異なる点数をつけました。私は1点を3回つけています」 |
| 研究員C |
「ランディ様の『文章力』に5点をつけました。我々3人全体で5点がついたのはこれだけですね。私は4点という点数はつけていません。ゼフェル様の『論理性』には2点をつけました。我々3人全体では2点を8回つけています」 |
|
ヒントをよく読んで、わかるところから埋めていきましょう。
ああ、その前に、7点の分け方は(1・1・5)、(1・2・4)、(1・3・3)、(2・2・3)の4とおりだということは確認しておいてくださいね。
さて、初めに研究員3人の発言を検討しましょう。
研究員Aの発言からマルセルの『着眼点』と『論理性』はすぐ決まります。
次に、研究員Bの発言です。
彼は『論理性』の要素には3人にすべて異なる点数をつけたと言っています。
7点を振り分けてすべて異なる点数ということは、1点、2点、4点ということです。
そして、彼はゼフェルにはすべての要素に3点以上つけたというのですから、ゼフェルの『論理性』は4点です。
研究員Cの発言からは、ランディの『文章力』が5点、ゼフェルの『論理性』が2点ということがわかります。
5点がついた『文章力』は、他の2人は1点だということになります。
ここまでのところをまとめると、こうなります。
| 研究員A |
| ・ |
着眼点 |
論理性 |
文章力 |
小計 |
| マルセル |
4 |
4 |
・ |
・ |
| ゼフェル |
・ |
・ |
・ |
・ |
| ランディ |
・ |
・ |
・ |
・ |
| 研究員B |
| マルセル |
・ |
・ |
・ |
・ |
| ゼフェル |
・ |
4 |
・ |
・ |
| ランディ |
・ |
・ |
・ |
・ |
| 研究員C |
| マルセル |
・ |
・ |
1 |
・ |
| ゼフェル |
・ |
2 |
1 |
・ |
| ランディ |
・ |
・ |
5 |
・ |
さて、これを元にしていろいろ考えてみましょう。
研究員Aの発言を見ましょう。
『着眼点』『論理性』の残り2人は1点、2点ですから、彼が3点を2回つけたというのは『文章力』で、内訳は(3・3・1)となります。
研究員Bの発言からはどうでしょうか。
1点を3回つけているうちの1回は『論理性』のところですから、あと2回です。
研究員Cの発言から、(5・1・1)はありません。
したがって、『着眼点』『文章力』の内訳は(4・2・1)か(3・3・1)かになります。…(X)
研究員Cの発言を見ましょう。
4点をつけていないというのですから、『論理性』の内訳は(3・2・2)です。…(Y)
『着眼点』の内訳は(3・3・1)か(3・2・2)ですね。…(Z)
次は…研究員Cが2点の総数は8回だと言っていますから、これを検討してみましょう。
すでにわかっている2点は研究員Aが2回、研究員Bが『論理性』で1回、研究員Cは『論理性』で2回です。
あと3回ですね。
研究員Aはもう2点はありませんから、研究員BとCで残りの3回をつけています。
研究員BとCの不明なところの可能性、(X)(Z)から、この3回がどうなるのかを考えましょう。
研究員Bが『着眼点』『文章力』でと2点をつける可能性は、2回、1回、0回です。
研究員Cの『着眼点』では2点をつける可能性は2回か0回です。
つまり、あと3回2点をつけるためには、
研究員Bの『着眼点』『文章力』は、どちらがどちらかはまだわかりませんが(4・2・1)と(3・3・1)、研究員Cの『着眼点』は(3・2・2)となる、ということです。
研究員の発言からわかるのはここまでです。
あとは、他のを検討して、わかるところをジワジワと埋めていきましょう。
ヒント3)から、ランディの『論理性』を考えます。
研究員Aは1点か2点、
研究員Bは1点か2点、
研究員Cは(Y)から2点か3点です。
つまり、ランディの『論理性』は2点、ということですね。
これで、『論理性』の欄が全部決まります。
| 研究員A |
| ・ |
着眼点 |
論理性 |
文章力 |
小計 |
| マルセル |
4 |
4 |
・ |
・ |
| ゼフェル |
・ |
1 |
・ |
・ |
| ランディ |
・ |
2 |
・ |
・ |
| 研究員B |
| マルセル |
・ |
1 |
・ |
・ |
| ゼフェル |
・ |
4 |
・ |
・ |
| ランディ |
・ |
2 |
・ |
・ |
| 研究員C |
| マルセル |
・ |
3 |
1 |
・ |
| ゼフェル |
・ |
2 |
1 |
・ |
| ランディ |
・ |
2 |
5 |
・ |
マルセルの得点はバラバラですから、ヒント4)にも当てはまってます。
ランディの『論理点』が決まりましたから、ここでヒント6)を考えましょう。
研究員Aのランディが6点以上を取るためには、
『着眼点(4・2・1)』が1点か2点、『文章力(3・3・1)』は1点か3点ですから、『文章力』は3点に決まります。
さらに、研究員Cのマルセルの『文章力』は1点ですから、ヒント4)から、研究員Aの『文章力』はゼフェル1点、マルセル3点となります。
また、研究員Bのマルセルの『文章力(4・2・1か3・3・1)』は1点でも3点でもありませんから、内訳(4・2・1)になります。『着眼点』が(3・3・1)ですね。
次に、研究員Cの『着眼点(3・2・2)』を考えてみましょう。
ヒント5)から、ゼフェル3点、マルセル2点はありません。
3点はランディかマルセルで、ゼフェルは2点で決まりです。
| 研究員A |
| ・ |
着眼点 |
論理性 |
文章力 |
小計 |
| マルセル |
4 |
4 |
3 |
11 |
| ゼフェル |
・ |
1 |
1 |
・ |
| ランディ |
・ |
2 |
3 |
・ |
| ・ |
1・2 |
・ |
・ |
・ |
| 研究員B |
| マルセル |
・ |
1 |
・ |
・ |
| ゼフェル |
・ |
4 |
・ |
・ |
| ランディ |
・ |
2 |
・ |
・ |
| ・ |
3・3・1 |
・ |
4・2・1 |
・ |
| 研究員C |
| マルセル |
・ |
3 |
1 |
・ |
| ゼフェル |
2 |
2 |
1 |
5 |
| ランディ |
・ |
2 |
5 |
・ |
| ・ |
2・3 |
・ |
・ |
・ |
確定できるのはここまでですね。
あとは、今わかっていないところの点数を考えていくのですが、これは、
ヒント2)3人のうち、総得点が1番高かった人と2番目に高かった人の得点差は1点でした。
ヒント6)ランディの小計は、研究員3人とも6点以上で、総得点は奇数でした。
を満たすように考えながら、試行錯誤していきましょう。
答えはこうなります。
| 研究員A |
| . |
着眼点 |
論理性 |
文章力 |
小計 |
| マルセル |
4 |
4 |
3 |
11 |
| ゼフェル |
2 |
1 |
1 |
4 |
| ランディ |
1 |
2 |
3 |
6 |
| 研究員B |
| マルセル |
1 |
1 |
2 |
4 |
| ゼフェル |
3 |
4 |
4 |
11 |
| ランディ |
3 |
2 |
1 |
6 |
| 研究員C |
| マルセル |
3 |
3 |
1 |
7 |
| ゼフェル |
2 |
2 |
1 |
5 |
| ランディ |
2 |
2 |
5 |
9 |
総合得点は
マルセル…22点、ゼフェル…20点、ランディ…21点
ですから、ヒント2)も満たしていますね。
いかがでしたか。
少しややこしかったかもしれませんね。
でも、ややこしいことを解きほぐしていくのは、頭の体操としてはとってもいいんですよ。
子供たちは、ずいぶん苦労をしていましたけれど、なんとか答を出しました。
3人寄ればなんとか、と言いますからね。
えーと、解答はこんなところですが、よろしいですか?
は〜い、ルヴァ様ありがとうございました。
応募してくださった方には正解数に応じてポイントを差し上げています。
今回までの得点はここをご覧ください⇒
※応募された方にはそれぞれにメールで結果と獲得ポイントをお知らせしています。
正解発表後2日ほどしても届いていないという方はメールアドレスの間違いなどの可能性がありますので、
こちらまでお問い合わせください。⇒ GO!
次回、第147回の問題編は、12月2日ぐらいの予定です。
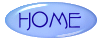
|