それでは第127回の解答&解説です。
解説はおなじみ地の守護聖ルヴァ様です。
それではルヴァ様、よろしくお願いします。
A1
はいは〜い。では1問目から考えてみましょうね。
ある建物の2階に照明用に電灯が3箇所設置されています。
そのスイッチは1階にあるのですが、表示が取れてしまって、3個あるスイッチのどれがどの電灯のスイッチなのかがわかりません。
さて、問題です。
どれがどの電灯のスイッチなのかを確かめる作業を1人でします。
階段を上り下りする回数をなるべく少なくしたいのですが、
最低何回階段を上り下りすればわかるでしょうか。
こんな問題でしたね。
状況はおわかりですか。
2階に電灯が3箇所、1階にスイッチが3個。
どのスイッチがどの電灯のものかを1人で確かめるのですね。
2人でやるなら簡単ですけれど、1人でやるとなると、階段を上がったり下りたりしないといけません。
さて、どうしますか?
スイッチを1つONにして、階段を上がって、どの電灯が点いているかを見ればそのスイッチがどの電灯のものかわかりますね。
え?
じゃあ、それを3回繰り返したら3つとも全部わかる、ですか?
ええ、確かに3回上ればわかりますけれどね、それだと無駄がありますよ。
3組のうち2組までわかったら、残った1組は自動的に決まるじゃないですか。
では2回上ればわかるということでいいのでしょうか。
それでは当たり前過ぎてパズルにはなりませんねえ。
ということで、1回上ればわかる、ということが可能かどうか考えてみましょう。
スイッチを1つONにして、階段を上がってみましょう。
今点いている電灯のスイッチがどれかはわかっています。
点いていない2つの電灯に何か区別がつけばいいのですよね。
点いていない2つの電灯。
さて、何か区別をつける方法があるでしょうか。
ここで、電灯の、といいますか、電球の特徴を考えてみましょう。
1番はもちろん「光を放つ」ですね。
このことで電灯の1つは見分けがつきました。
他には「熱を出す」ということがあります。
ずっと点いていた電球は熱くなっています。
どのくらい熱くなるかは電球の種類によって異なりますが、どれも熱くはなります。
これを使ってみましょう。
スイッチを1つ(仮にこれをAとしましょう)ONにしてしばらく待ちます。
AをOFFにし、別のスイッチ(仮にこれをBとします)をONにして、2階に行きます。
点いている電灯のスイッチがB、
消えている電灯のうち、さわって熱くなっている電灯のスイッチがAです。
熱くないほうの電灯のスイッチは、残った3つ目のスイッチですね。
これで3つともわかりましたから、答は、「1回上ればいい」となります。
いかがですか?
え?
電灯が触れないほど高いところにあったらどうするか、ですか?
あ〜、そういうときには脚立でも用意して行っていただきましょうか。
ということで、答は
1回上がればわかる でした。
A2
では、第2問を考えてみましょう。
こんな問題でした。
新しく開発された素材の見本が100個あるので、A〜Eの5つの箱に分けて入れたい。
次の条件に合うようにするには、どの箱に何個入れればいいのか指示してほしい。
1)どの箱にも5個以上は入れる。
2)どの箱の個数も7で割り切れてはいけない。
3)Aの箱にはDの箱の個数より8個少なく入れる。
4)Bの箱にはDの箱の個数の半分を入れる。
5)Cの箱に入れる個数は自乗数(1、4、9、16、…、81、100)。
6)どれかの箱には17個入れる。
条件をよく読んで、考えていってくださいね。
さあ、どこから手をつけましょうか。
まず、
3)と4)からA、B、Dの関係を確認しておきましょう。
Aは(D−8)個です。
DはBの2倍、2Bです。
ならばAは(2B−8)ということになりますから、
A+B+Dは(2B−8)+B+2B で、(5B−8)ということになります。
ここから、
A+B+Dは、
Bが8個のとき 32個、
Bが9個のとき 37個、
Bが10個のとき 42個l
などと計算できます。
(Bが5個、6個の場合はAが5個以上になりませんし、Bは7個ではありません←条件1・2)
さて、次に条件6)を考えましょう。
17個入った箱はどれでしょう。
AとDは偶数ですから、違います
Bが17個だとすると、A+B+Dは77個です。
とするとC+Eは23個、23以下のCの可能性は、16、9 です。
Cが16の場合、Eは7で、条件2)に合いません。
Cが9の場合、Eは14で、これも条件2)に合いません。
従って、Bは17個ではありません。
17は自乗数ではありませんから、Cも違います。
つまり、17個入っているのはEの箱、ということですね。
ならば、A、B、C、Dの合計は 100−17 で83個となりますから、
83から(5B−8)を引いた残りが自乗数になればいいわけです。
考えてみましょう。
A+B+Dは、
Bが8個のとき 32個、 ⇒ 83−32 …51
Bが9個のとき 37個、 ⇒ 83−37 …46
Bが10個のとき 42個、 ⇒ 83−42 …41
Bが11個のとき 47個l、 ⇒ 83−47 …36
Bが12個のとき 52個、 ⇒ 83−52 …31
Bが13個のとき 57個、 ⇒ 83−57 …26
Bが15個のとき 67個、 ⇒ 83−67 …16
Bが16個のとき 72個、 ⇒ 83−72 …11
この中でCが自乗数になるのは36個と16個の2通りです。
それぞれの内訳をみてみましょう。
Bが11個のとき A14個、C36個、D22個、E17個
Bが15個のとき A22個、C16個、D30個、E17個
7で割り切れてはいけないのですから、14個はありません。
従って、すべての条件を満たすのは1通りだけです。
これが答えですね。
まとめておきましょう。
A…22個
B…15個
C…16個
D…30個
E…17個
いかがでしたか。
条件を整理していけば、そんなに大変な問題ではないでしょう?
えーと、解答はこんなところですが、よろしいですか?
は〜い、ルヴァ様ありがとうございました。
応募してくださった方には正解数に応じてポイントを差し上げています。
今回までの得点はここをご覧ください⇒
※応募された方にはそれぞれにメールで結果と獲得ポイントをお知らせしています。
正解発表後2日ほどしても届いていないという方はメールアドレスの間違いなどの可能性がありますので、
こちらまでお問い合わせください。⇒ GO!
次回、第128回の問題編は、7月8日の夜ぐらいの予定でしたが、
11日の夜くらいになりそうです…
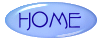
|