HAPPY EVENT 2009.2.15
王立図書館から戻ってきて、自分の執務室に向かう途中、聖殿の廊下でルヴァはふと足を止めた。
どこかから話し声が聞こえてくる。
見回しても周囲に人影はなかった。
どうやら、どこかで女官たちが話しているのが、風に乗って聞こえてくるらしい。
そのまま立ち去ろうとしたルヴァは、「オスカー」という言葉が耳に入ってもう一度足を止めた。
物音を立てないようにして、そっと耳を澄ます。
聞かれているとも知らず、女官たちの話は盛り上がっていた。
時折り「キャァ〜」とか、「え〜?」などの声が上がる。
話の内容を聞き取って、ルヴァは微かに瞳を曇らせた。
女官たちの話し声が遠ざかっていった後も、まだルヴァはそこに立ち尽くしていた。
「ルヴァ、どうかしたのか」
背後から声が掛かった。
ルヴァはびっくりして振り返る。
オスカーがキザな笑顔を浮かべて立っていた。
「オ、オスカー…」
「やぁ、ルヴァ」
オスカーはにっこり笑うと派手なウインクを飛ばしてきた。
冗談だとわかっていてもドキッとしてしまう。
そんなルヴァの心も知らぬげに、オスカーは心配そうな顔付きになってルヴァを見詰めた。
「立ち止まったまま全然動かないから、何かあったかと思ったんだが…」
「あ、ああ…いえ、なんでもありません。ちょっと…あの、疲れたので一休みしていたところです」
「そうか」
オスカーはルヴァが抱えた本の山に視線を走らせた。
「そんな荷物を抱えているから疲れるんだぜ。図書館のヤツらに運んでもらえばいいのに」
「でも…すぐに読みたいものばかりですから」
焦ってルヴァが答えると、オスカーはクスッと笑った。
「そんなこと言ったって、これだけの本を同時に読むのは無理だろ」
「え、ええ…でも…」
「読みたい本は手放したくない、か。ま、あんたらしいよな。貸せよ。俺が運んでやる」
言うやいなや、オスカーはルヴァの手の中から、本の山を取り上げた。
「いえ、自分で運べますから…」
「遠慮するな。これくらいなんともない」
「でも…」
「手ぶらが気になるなら、このファイルを持ってくれると助かる」
本を抱えた手の先には、分厚い書類のファイルが指先に挟まれていた。
今にも落ちそうで危なっかしい。
ルヴァは慌ててそのファイルを抜き取った。
「あ、あの…」
「行き先はあんたの執務室でいいのか?」
「あ…、はいっ」
「そうか。じゃあ行くぞ」
オスカーは地の執務室に向かって力強い足取りで歩き始めた。
呆然としていたルヴァは、一瞬の後、ハッとしてオスカーの後を追い掛ける。
オスカーの手によって、本の山は無事執務室の机上に運ばれた。
「あの…ありがとうございました」
「これくらいなんてことないさ。いつでも言ってくれ」
「ありがとうございます」
「ルヴァ…」
「はい」
「あ〜その…なんだ…」
「はい?」
オスカーにしては歯切れが悪い。
ルヴァは首を傾げてオスカーを見た。
「ルヴァ…今夜、何か用事があるか?」
「え? …いえ、別に何もありませんけれど…。新しく届いた本を読むつもりでいるくらいで…」
「その…俺がディナーに招待したら受けてくれるか?」
「あなたが…私を、ですか?」
「ああ。来てくれると嬉しい」
「だって、今日は…」
ルヴァは口ごもる。
今夜、オスカーは誰か大切な人と過ごしたりはしないのだろうか。
ルヴァはオスカーの様子をそっとうかがう。
オスカーは…ルヴァをじっと見ていた。
「今日がどうかしたのか?」
「いえ…あの…」
「来てくれるか?」
「あ…はい」
オスカーの勢いに飲まれたように、ルヴァは思わずうなずいていた。
途端に、オスカーは満面の笑みになる。
「そうか。じゃあ迎えの馬車をやるから」
「あ、あの…」
「それじゃ、今夜。楽しみにしてるぜ」
オスカーはそれだけ言うと、ファイルを手に出ていった。
後を見送って、ルヴァは小さくため息をついた。
オスカーはどういうつもりなのでしょう…
まさか、ルヴァが胸に秘めた思いを知っているわけではあるまい。
他の日ならともかく、どうして今夜なのだろう…
考えても答は出なかった。
実際に炎の館から迎えの馬車が来るまで、まだ半信半疑だった。
馬車に揺られながら、ルヴァはドキドキと鼓動が早くなるのを感じていた。
オスカーは笑顔で出迎えてくれた。
聖殿で見せる公の雰囲気とは違うラフな感じにドキッとする。
ディナーはルヴァの好みに合わせたようなメニューだった。
どれも素材の良さが充分に活かされて美味しかった。
美味しそうにルヴァが食べる様子を、オスカーは微笑んで見詰めているようだった。
ディナーが済むと、場所を変えてお茶になった。
「うちのディナーはどうだった。気に入ってもらえたか」
「ええ、とっても美味しかったです」
「そうか。それは良かった」
それだけ言って、オスカーはお茶を飲み始める。
お茶を味わいながら、ルヴァは不思議そうにオスカーを見詰めた。
ディナーの間は、食卓にふさわしい軽い話題に終始していた。
なぜ今夜招待されたのか、まだわからない。
オスカーの意図はどこにあるのだろう…。
オスカーが目を上げて、視線がぶつかった。
オスカーがフッと笑う。
「どうかしたか?」
「いえ…ただ…」
「ただ、何?」
「どうして今夜ご招待いただいたのだろうと思って…」
「そうか…」
オスカーの表情が引き締まる。
ルヴァは思わず息を呑んだ。
「ルヴァは、今日が何の日か知っているか?」
ドキッとした。
それを抑えて、何でもないように答える。
「ええ。この習慣もいつの間にか聖地に定着してしまいましたね」
「そうか。知っているのか」
オスカーは何か考えているような眼差しでルヴァを見る。
ルヴァは、昼間から気になっていたことを、つい口に出した。
「あの、オスカー…」
「ん?」
「聖殿の女官たちが、今年はオスカーはチョコレートを受け取ってくれないと話していましたが…」
「耳が早いな」
オスカーはフッと笑った。
「今年だけじゃない。俺はもうこれからはチョコを受け取らないことにしたんだ」
「どういうことです?」
「欲しいのは1人からだけだから、その人以外からはたとえ義理チョコでも受け取らないと決めたんだ」
「そうですか…」
まさかと思っていたことが確信に変わる。
つまり、オスカーは本当に好きな人が出来たということなのだ。
その人からのチョコしか受け取らないというのだ。
ルヴァはそっとポケットを押さえた。
その中には、ひょっとしたら渡せるかもしれないと思って用意した小さな包みがある。
やはり、渡すことは出来なそうだ。
ならば、このままそっと持って帰ればいい。
自分の思いを知られていないのは幸いだ。
これからもずっと、この思いは自分の胸の中に秘めておこう…。
ルヴァは、自分の胸の中を覗き込む。
オスカーのことを意識しだしたのはいつのことだったろう。
オスカーの一挙一動が気になって、
オスカーが誰かに微笑みかけているとそれだけで胸に痛みを感じる気がして、
オスカーに話しかけられるだけでドキドキして…。
自分がオスカーを「好き」なのだと認識したのは、もうずいぶん前だ。
そんな思いを伝えられるはずもないから、自分の胸の中だけにそっと閉じ込めていた。
そして、これからもずっと閉じ込めておくのだ…。
「ルヴァ…」
オスカーの声で、ルヴァは物思いからハッと現実に戻ってきた。
視線を上げるとオスカーがルヴァを見詰めていた。
真剣な表情だった。
「ルヴァ…」
再びオスカーがルヴァの名を呼んだ。
オスカーの声が、さっきまでと違う。
ルヴァの胸の奥が電流が走ったようにズキンとした。
「ルヴァは俺に何かくれないのか?」
「え…?」
「俺にチョコをくれる気はないのか?」
「あの…」
オスカーは何を言っているのだろう…。
さっき、1人から以外、誰からも貰わないと言っていたのに。
え? まさか…
まさか、その1人がルヴァだということがあるだろうか…
そんな…
「ルヴァ…」
いつの間にかオスカーがすぐ傍にきていた。
息のかかるほどの距離で、オスカーはルヴァを見詰めている。
「あ、あの…」
反射的に後ろに下がろうとして、ルヴァは、オスカーの手がルヴァの腰を捉えていることに気が付いた。
「あの…オスカー…」
「ずっとルヴァのことを見てきたんだ。だけど、あんたは俺なんか全然相手にしていないから…。忘れようとして何人ものレディたちと付き合ってみたが、やっぱりあんたのことが好きだってことがわかっただけだった」
ルヴァは自分の耳を疑った。
今、聞いていることは本当のことだろうか。
都合の良い夢をみているのではないだろうか…
「ルヴァ、俺はあんたの後輩以上のものにはなれないのか? 俺はあんたの特別にはなれないのか?」
オスカーはルヴァを抱き締めた。
「オ、オスカー」
渾身の力で、ルヴァはオスカーを突き放した。
オスカーは呆然としてルヴァを眺める。
「…ダメ…なのか…?」
シュンとするオスカーは、頼りなげな子供のようだった。
ルヴァは慌てて首を振る。
「そうじゃないんです。そうじゃなくて…」
ポケットを探る手が震える。
ようやく引っ張り出した包みは、リボンが緩んで解けそうになっていた。
「あの…オスカー…私の気持ちです。受け取っていただけますか…」
消え入るような声で言って、包みを両手で差し出す。
オスカーは信じられないというように、目を丸くした。
「それ、ひょっとして…俺へのチョコ、か?」
ルヴァは、オスカーを見詰めたままコクンとうなずく。
オスカーが一気に歓喜の表情に変わる。
「信じられない…」
ポロリとつぶやいた言い方がひどく素朴だったので、なんだか可愛いとルヴァは思った。
「夢みたいだ…。嬉しい」
オスカーは受け取ったチョコを握り締めてそう言った。
ルヴァはふわりと笑う。
「『義理』じゃないですからね」
そう言ったらなぜだか涙がこぼれた。
アッと思った時には、オスカーに抱き締められていた。
それでも涙は止まらず、ルヴァはオスカーにしがみついて泣いていた。
「改めて言う。ルヴァが好きだ」
正面から向かい合って、オスカーが儀式のように厳かに言った。
「私も…あなたのことをずっと思ってきました」
同じようにルヴァも言う。
オスカーがちょっとだけ肩の力が抜けたように笑った。
「今は?」
「もちろん今もです」
ルヴァもクスッと笑って答える。
オスカーがつっと近付いてルヴァを抱き締める。
しっかりと抱き締めた後、オスカーはおもむろにルヴァの耳元でささやいた。
「で、どうするんだ? 『手をつなぐ』あたりから始めればいいのか? それとも『今夜は泊まっていってくれるだろうな』と甘くささやけばいいのか?」
「オスカー…」
抱き締められたまま、ルヴァは幸せそうに微笑んだ。
そして、そっと答える。
「あなたのお好きな方で…」
 Happy Valentine ! Happy Valentine !
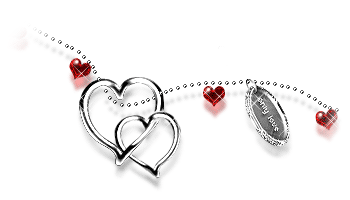
バレンタインのお話でした。
15日朝に書き始めました。当然のごとく遅刻です(笑)
今年のお相手はオスカー様です。
初々しい初めて話で(笑)
強気なのか弱気なのかわからないオスカー様がポイントです。
 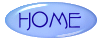
|